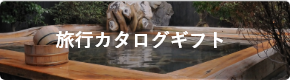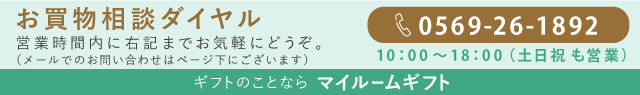結婚内祝い、いつまでに贈る?お祝いをもらった時期で変わるマナーとは。

結婚祝いをいただいたとき、お礼に結婚内祝いとしてお返しの品を贈ることは、一般的なマナーとなっています。 では、結婚内祝いはいつまでに贈ればよいのでしょうか? 以下では結婚内祝いを贈る時期について解説しています。 2人の門出を祝ってくれている人のためにも、正しくマナーを理解して失礼のない贈り方をマスターしましょう。
結婚内祝いを贈るタイミングは?
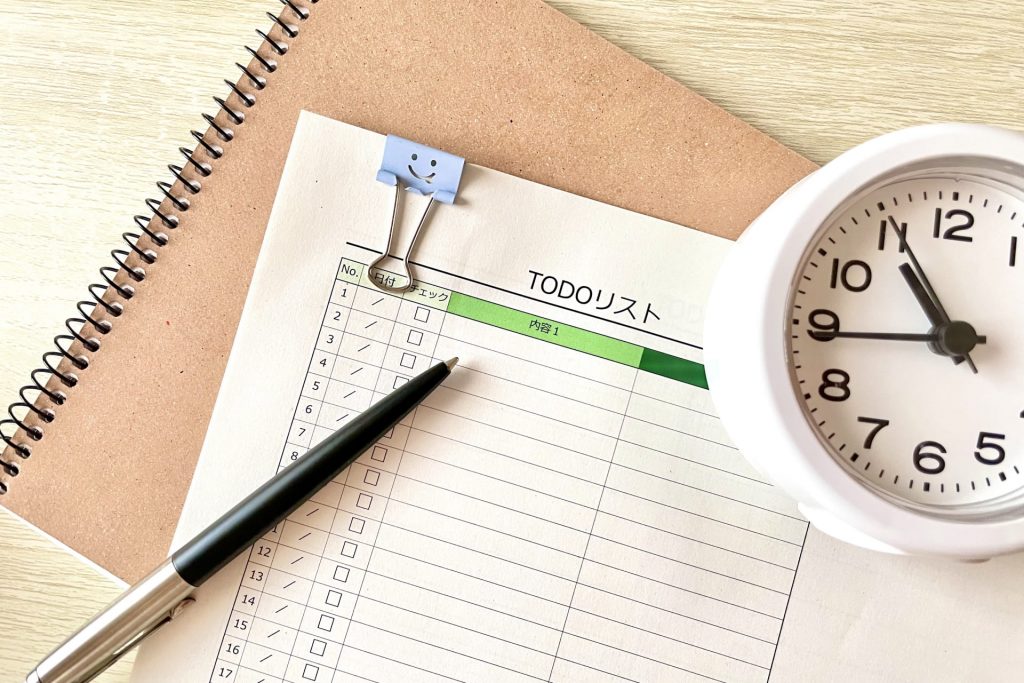
一般的に結婚の内祝いを贈る時期は、お祝いをいただいた時を基準に考えて1カ月以内がマナーとされています。なるべくなら2週間から3週間くらいの間がベストタイミングです。何を贈るのかも大事ですが贈る時期も大切です。しかし、入籍をした前後は、引っ越しや式の準備などでなにかと忙しいものです。結婚内祝いを選ぶ時間が十分にないことも珍しくありません。忙しい場合には、結婚内祝いに先だってお礼だけ伝えておけば、トラブルを避けることができるでしょう。マナーをしっかり確認しましょう。
結婚祝いをバラバラの時期にもらったときはどうすればよいのでしょうか。
まとめて対応するべきか、それとも個別に時期を見計らって贈るべきか、判断に迷う人が多いのではないでしょうか。結婚式前後にもらった場合は、それぞれもらった日から数えて1ヶ月前後を目安に贈るようにしましょう。
入籍時に近い時期にいただいた場合は、結婚式後に贈って大丈夫です。ただし、入籍時期と挙式の時期が大きくずれる場合には、前もって相手に伝えておくとようにしましょう。バラバラの時期にお祝いをもらったとしても、基本的には結婚内祝いはなるべく速やかに贈るのがマナーです。遅れてしまうと「喜んでもらえなかった」あるいは「お祝いを渡したことを忘れているのではないか」といった気持ちを、お祝いをくれた人に与えてしまう可能性があるからです。1日でも早く感謝が伝えられるように、結婚内祝いは早くから準備しておきましょう。
なお、返礼品としての結婚内祝いの相場は、結婚祝いの半額ほどが相場です。ただし、目上の方や親族などから高額な金額の結婚祝いをいただいくこともあるかと思います。新生活を始めると何かとお金がかかるものです。必要な物をといただいたのに半額の返礼品を贈ると失礼にあたりますので注意してください。高額な場合贈る品物選びは時間がかかってしまいます。親からお礼の連絡を伝える習慣のある地域もあるため、親族の場合の返礼品は一度両親に相談してみるのがいいと思います。
より詳しい結婚内祝いマナーについては弊社Myroom GIFTのホームページにて紹介しているので、そちらを参考にしてください。
内祝いを贈る時期(ケース別編)

お返しを贈る時期は、結婚式のタイミングによっても変わります。
以下では結婚式までの時期や式を挙げない場合など、3つのケースに分けてお返しの時期を解説します。
結婚式を挙げる際は式後1カ月が目安!
結婚式の前にお祝いをいただくこともあると思います。結婚式以前にもらったお祝いに対しては、結婚式後1カ月を目安に結婚内祝いを贈るとよいでしょう。早すぎても遅すぎてもNGです。
しかし、一般的に結婚式を催す場合は、招待客への引き出物が内祝いになります。
そのため、引き出物を渡せなかった方、結婚式に出席いただけなかった方、招待していないもののお祝いを届けてくれた方には、結婚内祝いを別途贈るとよいでしょう。
また、ご祝儀やお祝いが高額で、引き出物だけではお返しの品として不十分な場合にも、結婚内祝いという名目でお返しの品を贈ります。
結婚式はまだまだ先の場合は?
新型コロナウイルスの影響もあり結婚式がいつできるのかわからない方もいるかと思います。結婚祝いを頂いたものの、結婚式が半年以上先のときには、結婚内祝いはいつ贈ればよいのでしょうか。結婚式がまだまだ先であっても、結婚内祝いを贈る時期は結婚式から1カ月後を目安にしてかまいません。ですが、数カ月以上たってから内祝いを贈ると「今頃になって?」と驚かれるかもしれないので注意が必要です。トラブルを避けるためにも、結婚内祝いが遅くなるときは、お礼の言葉だけでも先に伝えておくようにしましょう。
結婚式に招待する予定の人は、結婚式のときに引き出物を手渡せば、内祝いの代わりになります。そのため、招待予定の人には、あらかじめ「結婚式に招待する」と伝えておくようにしましょう。もし招待予定にない方からお祝いをもらったときは、お祝いをもらった日から1カ月以内に内祝いを贈るようにしましょう。
結婚式を挙げない場合は1カ月がマナー!家族婚や結婚式の予定が決まっていない場合は?
結婚式を挙げる予定がない場合は、基本通りお祝いをいただいたときから1カ月ほどの期間でお返しの品を贈るのがマナーです。また、家族婚のように身内以外の人を結婚式に招待する予定がない場合も同じです。家族婚の場合は、身内だけで式を挙げる旨を、お祝いをくれた人に伝えておくとよいでしょう。
では、結婚式を挙げるつもりはあるが、予定が決まっていない場合はどうすればよいのでしょうか。予定がまだ立っていない場合には、お祝いの品をもらったときから1カ月ほどの期間で、結婚内祝いを贈るようにしましょう。たとえ、将来に必ず結婚式をするつもりであったとしても、心づかいにお礼をしないで長期間放置するのは、マナーとしてふさわしくありません。
もし、結婚式を予定していたが中止になってしまった場合、結婚内祝いはどう贈ればよいのでしょうか。まだ結婚内祝いを贈っていないのであれば、事情を伝えた上でお返しの品を贈るようにしましょう。贈るタイミングは、結婚式の中止が決まった後、なるべく早い時期がよいでしょう。人には誰しも事情があるものなので、結婚式中止の事情を説明すれば、ほとんどの人は納得してくれるでしょう。
なお、不祝儀として贈るわけではないので、熨斗は結婚内祝いのものを使います。仲の良い人や親族ならば、新婚旅行のお土産を内祝いの代わりに手渡すのもよいでしょう。ただし、お土産だと結婚祝いのお返しの品であることがわかりにくくなってしまうので注意が必要です。
お返しを贈る前に気を付けたいマナー

結婚祝いを受け取った後は、ただお返しの品を結婚内祝いとして贈ればよいというものではありません。お返しを贈る前にはいくつかの気を付けたいマナーがあります。
お礼と結婚内祝いは別にしよう!お礼の伝え方は相手によって異なる
結婚祝いをいただいた後、最初にするべき行動は結婚内祝いの送付ではありません。真っ先にお礼の言葉を伝えるようにしましょう。「お返しの品を贈るからあいさつはする必要がない」と考えている人もいますが、気持ちは言葉にして伝えなければ通じるものではありません。また、感謝の気持ちを伝えることと、感謝の気持ちを形にして受け取ってもらうことは、まったく別のことです。お礼はなるべくなら直接伝えるのがおすすめ。感謝の気持ちが伝わりやすいからです。お礼を伝えるときは、相手との関係性や距離の近さによって、連絡手段を変えるとよいでしょう。
上司や同僚あるいは友人など、頻繁に出会う人にお礼の言葉を伝えるときは、顔を見合わせた時に直接お礼を述べるとよいでしょう。親しい同僚であればLINEや電話で、言葉を伝えるだけでもかまいません。なお、結婚式への招待を予定しているときや、結婚内祝いを送付する時期が遅れる場合には、お礼と合わせて伝えておくようにしましょう。
遠方の知人や親戚関係など、すぐに会うことが難しい人の場合、電話でお礼を伝えても構いません。お礼状を贈るのもよい方法です。ですが、よほど親しい間柄でない限りは、メールやLINEでお礼を伝えるのはやめておいた方がよいでしょう。頻繁に顔を合わせることのない親しい人や友人なら、LINEやメールを送るのも良いでしょう。気心が知れた仲間であるなら、簡易な手法であっても、失礼だと捉えられることがないからです。むしろ、気さくに話し合えるツールでお礼を述べた方が、会話も盛り上がることでしょう。もちろん、電話で連絡してもかまいません。
結婚内祝いにはメッセージカードも忘れずに
結婚内祝いにはメッセージカードを添付するようにしましょう。メッセージは相手と自分たちとの関係性によって文面を変える必要があります。上司や目上の方への文面は、結婚祝いへのお礼から始まり、自分たちの将来の展望を書き添えた上でお礼の品を贈ることを伝え、これからも変わらぬ指導や付き合いをお願いする旨で締めれば、きれいなメッセージに仕上がるでしょう。しかし決まりきった言葉では、感謝の気持ちがなかなか伝わらないものです。そこで、メッセージには自分たちのエピソードを書き加えることをおすすめします。エピソードが追加されれば、メッセージが感情溢れる温度感のある言葉として伝わりやすくなります。
上司や目上の方への結婚内祝いで困ったときは「上司へ結婚内祝いを贈るときのマナー!タイミングや喜ばれる人気商品」を参考にしてください。上司に贈るメッセージに最適な文例も紹介しています。
上司へ結婚内祝いを贈るときのマナー!タイミングや喜ばれる人気商品
友人や親しい方へのメッセージは、上司や目上の方へ充てたものよりフランクに書いて構いません。ただし、次のような文面のマナーを守っておく必要があります。結婚内祝いのメッセージには「句読点を用いてはならない」というルールがあります。句点は文章の終わりに使われるため結婚生活の終わりをイメージさせ、読点は文章を区切るために使うものなので、縁を切ると捉えられるため、結婚内祝いのメッセージにはふさわしくありません。結婚内祝いのメッセージは1文がコンパクトになるようにイメージして書き、句読点を使う必要がない文章にしましょう。
一文が長くなるときは、句点や独点の代わりに空白のスペースを入れてください。句読点を用いた場合と変わらない、整った読みやすい文章になります。
他にも「忌言葉を使わない」「重ね言葉はタブー」「お返しという言葉は禁句」などのルールがあるので、メッセージを書く際には注意してください。具体的なメッセージの文例やより詳細な注意点は「友達への結婚内祝いにメッセージを添える時の注意点と具体的な例文」において解説しています。
友達への結婚内祝いにメッセージを添える時の注意点と具体的な例文
メッセージカードを出すときは、ぜひ弊社が提供しているメッセージカードのサービスをご利用ください。定型文を選ぶだけでシーンに適したメッセージカードが添付できます。
さらに、弊社Myroom GIFTでは、無料でギフトを包む包装用紙や熨斗(のし)紙をお付けしています。結婚内祝いの品には、熨斗を付けるのがマナーとなっており、紅白もしくは金銀の結びきりの水引で、表書きに「寿」あるいは「内祝い」と書くのが一般的です。熨斗下には新姓または新姓の下に夫婦の名前を並べて書きます。熨斗については「結婚内祝いの「のし」どうすれば良いの?書き方と基礎知識」で詳しく解説しています。
早すぎる時期のお返しも考えもの。お返しは適切な時期に贈ろう
結婚内祝いの品はなるべく早く贈る方がよいですが、あまりに早すぎるのは考えものです。内祝いが早く届きすぎると、お祝いとしていただいたものをすぐに返却するような形になるからです。さらに、お祝いを待ちかまえていたかのような印象を相手に与えかねません。早くても、結婚祝いをいただいたときから1週間は開けるようにしましょう。
プロのアドバイスを参考にしよう!

結婚内祝いを贈る時期は、お祝いを受け取ってから1カ月前後が最適です。しかし、結婚式の有無や時期によってもタイミングは変化するので注意してください。また、贈る時期が早すぎると相手に失礼になるので、お祝いをもらってから1週間くらい後にお返しの品を贈るようにしましょう。結婚内祝いにはさまざまなマナーがありますが、気を付けたいポイントは相手に失礼にならないように心がけることです。お返しの品を贈るまえに、必ず言葉でお礼を伝えるようにしましょう。
さらに、結婚内祝いにメッセージカードを添えて感謝の気持ちを表すことも大切です。近頃では結婚のあり方が多様化しているように、さまざまなシーンでマナーと呼ばれるものが変化しています。例えば、結婚内祝い自体も「身内への幸せのおすそ分け」という意味から、お礼の品という意味へと変化しています。今の時代のさまざまな情報があって悩んでしまうこともあります。結婚内祝いで困ったときはプロのアドバイスを参考にするのもよいでしょう。結婚内祝いに迷ったときは私ども「Myroom GIFT」にお任せください。
Myroom GIFTでは、結婚内祝いのほかにも、香典返しや出産内祝いなど、さまざまなシーンに応じたギフトを取り扱っています。